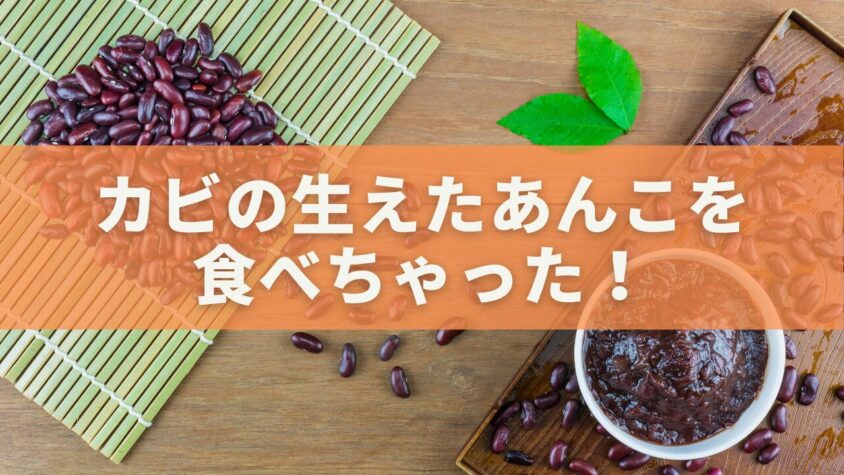日本の家庭になじみ深い「あんこ」ですが、適切な扱いを怠ると思わぬトラブルに見舞われることもあります。
今回は、あんこの正しい保管方法や、あんこ由来の食中毒について、あまり知られていない情報をお伝えします。
あんこにカビが生えてるけど腐っているの?
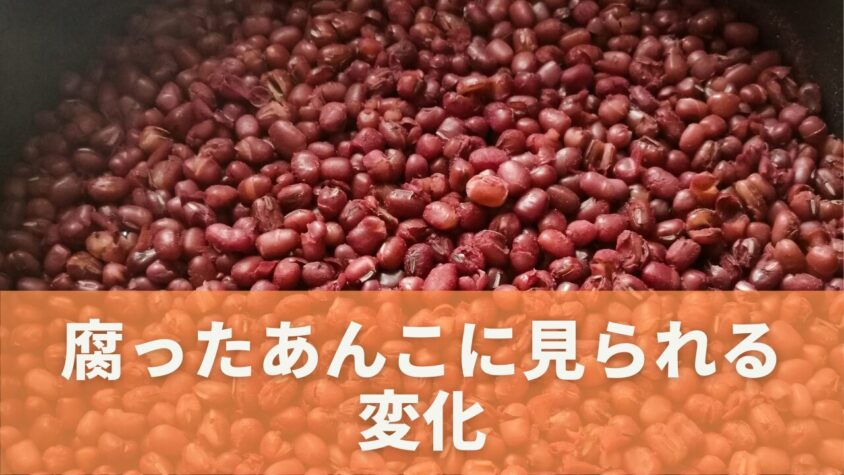
あんこが腐るとどのような変化が起きる?
湿度が高いと腐りやすいあんこは常温で放置すると早く劣化します。
手作りの場合、手や空気の触れる機会が多く、これが腐敗の原因になり得ます。時間が経つと水分が失われ、乾燥して固くなります。腐敗が進むと、緑や白のカビが生えることがあります。外見に変化がなくても、変わった臭いや酸っぱい味、粘り気が出た場合は食べるのをやめてください。
あんこの賞味期限はどれくらい?

市販のあんこの賞味期限について
あんこの種類や製造者によって賞味期限は異なり、糖度や封入方法によって左右されます。市販のあんこは一般に高い糖度で密封されているため、次のように長期保存が可能ですが未開封の場合に限ります。
- プラスチック袋入り:約2ヶ月~90日
- チューブ入り:半年~1年弱
- 真空パック:1年~最大2年
- 金属缶入り:最長3年
自家製あんこの推奨消費期限
家で作ったあんこは冷蔵保存でも「3日から1週間」が消費の目安です。
これ以上経過すると細菌が繁殖しやすくなりますので「1週間以内」に使い切ることをおすすめします。賞味期限前でも臭いや味がおかしければ食べない方が良いでしょう。
賞味期限切れのあんこの取り扱い方
賞味期限が1日~3日程度過ぎた未開封のあんこは、製造者の指示に従い食べることもありますが、香りや味にわずかな変化があれば食べるのは避けましょう。開封後は、冷蔵保管して1週間以内に使い切るのが良いです。
あんこによる食中毒のリスクとは?
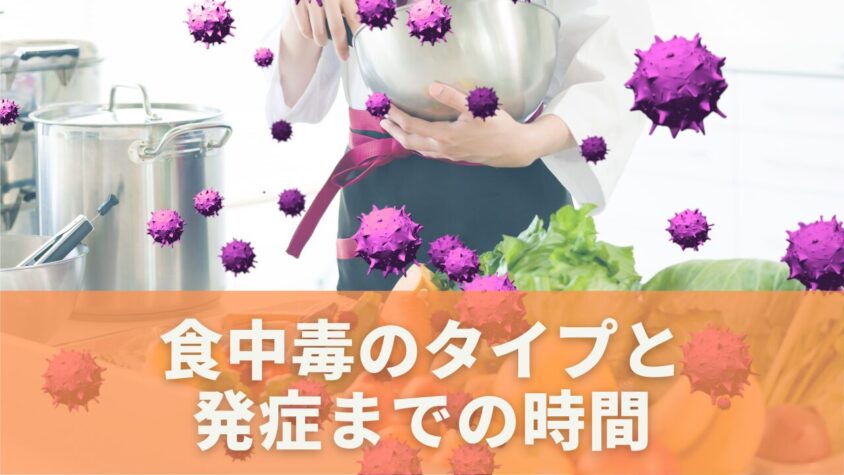
食中毒の原因|バチルス・セレウス菌
主な原因はバチルス・セレウス菌で、これはあんこの製造過程や室温での保管中に増殖し、毒素を生成して食中毒を引き起こすことがあります。28度~35度の温度範囲で増殖しやすいため、夏場は特に注意が必要です。
食中毒の症状について
食中毒には主に2種類の症状があります。
嘔吐を引き起こすタイプ(細菌性毒素型)と下痢を主症状とするタイプ(細菌性生体内毒素型)です。
日本では、バチルス・セレウス菌による食中毒は嘔吐型が多いです。
食中毒の発症タイミング
嘔吐型食中毒は通常潜伏期間が短く、30分~5時間(多くは1~3時間以内)で発症し激しい嘔吐が主な症状です。このタイプは耐熱性のセレウリド毒素によって引き起こされ、ブドウ球菌による食中毒に似ています。セレウリドは100度で30分間加熱しても失活しないため、予防が重要です。
下痢型は潜伏期間が8~16時間(通常は10~12時間)と長く、ウェルシュ菌による食中毒に似ており区別が難しいです。このタイプは食品中で増殖した菌を摂取することで発症します。
食中毒の予防策
セレウス菌の芽胞は耐熱性が強く、通常の加熱では破壊されにくいため、調理後の冷却過程での増殖を防ぐことが重要です。大量調理後は、食品を小分けにして速やかに冷却することが推奨されます。保存時は調理後2時間以内に冷蔵し、冷蔵状態では8℃以下、温かい状態では55℃以上を保つことが理想的です。
食中毒が引き起こす重篤なリスク
下痢型食中毒は主に腹痛や下痢を引き起こしますが、免疫力が低下している人が感染すると重篤な健康被害が発生することがあります。具体的には、急性の肝臓障害を引き起こす可能性があり、最悪のケースでは死亡することもあります。このため、このタイプの食中毒を避けるために適切な対応と警戒が必要です。
あんこを使用した和菓子の保存方法

おはぎやあんこを使用した和菓子は新鮮なうちが最も美味しいと言われていますが、余ってしまうこともあります。そんな時の適切な保存方法を紹介します。保存のポイントは清潔な環境での調理で使い捨て手袋の使用が基本です。
室内での保存法
おはぎは密封容器に入れて20℃以下の涼しい場所に保管すると、約半日~1日間品質を保つことができます。当日中に食べる場合は、常温保存でも問題ありません。一般的な和菓子は、お重や陶器、密閉できるプラスチック容器などに入れて常温で3日間保存が可能です。
冷蔵での保管方法
おはぎの中身がもち米や白米のため、冷蔵庫での保存はあまり向いていません。密閉して冷蔵すれば、風味は若干落ちますが1日~2日保ちますがなるべく早く食べることを推奨します。他の和菓子もでんぷん質を含むため、冷蔵庫内で乾燥しやすいので、ラップで包むと良いですが早めに食べることが望ましいです。
冷凍による長期保管
和菓子の長期保存には冷凍が最適です。
家庭用冷凍庫は通常-18℃に設定されており、これにより細菌の活動が抑えられます。おはぎや他の和菓子を個別にラップで包んでジップロックバッグに入れると、約1ヶ月間保存が可能です。解凍は自然解凍がベストで、数時間前に取り出して室温か冷蔵庫で解凍します。解凍後は当日中に食べてください。
総括
- あんこは時間が経つと乾燥し、最終的には緑や白のカビが生える可能性があります
- 外見に変化がなくても、異臭がある、味が酸っぱい、ネバネバする場合は食べるのをやめましょう
- あんこから生じる食中毒は主にセレウス菌が原因で、嘔吐や下痢が特徴です
- 嘔吐型は発症まで短時間(約30分~5時間)、下痢型はより長い潜伏期間(約8~16時間)があります
- セレウス菌は28℃~35℃で増殖しやすく、保存は8℃以下の冷蔵か、55℃以上の温度で行う必要があります
- おはぎや和菓子の保存は、即日消費なら室温が適切で、長期保管は冷凍がおすすめです