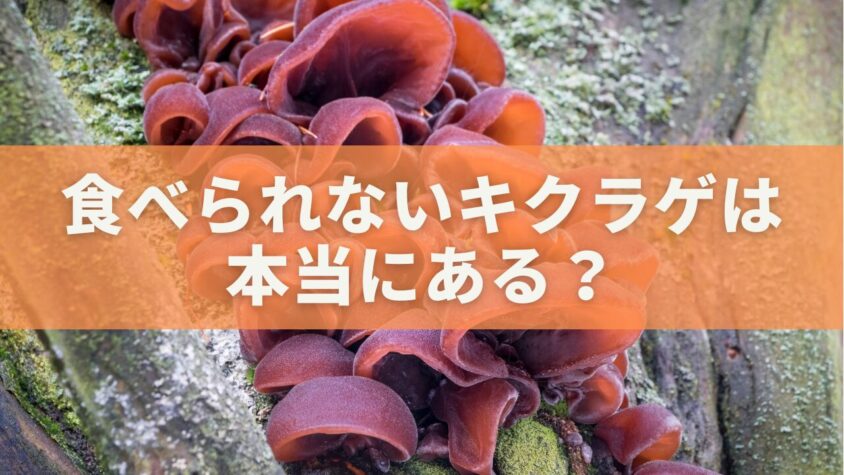東アジアの多くの料理で愛される独特な食感を持つ「キクラゲ」ついてご存知ですか?
実はキクラゲはキノコの一種で、キクラゲ目キクラゲ科キクラゲ属に分類されます。
春から秋にかけて、倒木や乾燥した木に自然発生するキクラゲは、日本、中国、台湾、韓国をはじめとする東アジア地域やミャンマーでよく食べられています。
中華料理や日本のラーメンなどで目にすることも多いでしょう。
この記事では、キクラゲの特徴や注意点について詳しく解説します。
食べられないキクラゲがあるって本当なの?毒性の有無について

キノコには食用に適した種類と、体に害を及ぼす種類が存在します。キクラゲにもいくつかの種類があり、その中に毒を持つものがあるのかという疑問は自然です。
キクラゲに毒はあるのか?
研究によれば、キクラゲ属のキノコには毒性が確認されていません。
一般に食されている
「アラゲキクラゲ」「シロキクラゲ」「ハナビラニカワタケ」などは毒性がない
とされており、安心して食べられます。
キクラゲに似た毒キノコに注意!
キクラゲと外見が似ているが、異なる分類に属する「クロハナビラタケ」は、毒キノコとして知られています。健康に悪影響を及ぼす可能性があり、特に危険なキノコの一つです。次章で特徴を解説します。
キクラゲに似た毒キノコ「クロハナビラタケ」の特徴

キクラゲと外見が似ているものの、有毒な「クロムラサキハナビラタケ」には注意が必要です。
クロハナビラタケ pic.twitter.com/2exgoWGgx8
— ふすべ (@OnifusubePhar) March 2, 2019
野生で見かけた場合は決して摂取しないでください。
ここでは、クロムラサキハナビラタケの詳細をご紹介します。
クロムラサキハナビラタケの特徴
クロムラサキハナビラタケは、ビョウタケ目ビョウタケ科に属する毒キノコです。
秋から冬にかけて広葉樹の倒木や枯れ木に発生し、深い黒色をしており、一般に小さい大きさで群生します。
このキノコは日本を中心に生息し、中国や朝鮮半島で見かけることもあります。
今日見つけたクロハナビラタケ pic.twitter.com/uh6gkwHz2e
— 帆立の貝焼き (@yakihota_529) March 23, 2020
摂取した際の健康への影響
クロムラサキハナビラタケには消化器に有害な毒が含まれています。万が一摂取すると、胃痛、下痢、吐き気などの消化器系の症状が現れる可能性があります。
キクラゲとクロムラサキハナビラタケの見分け方
キクラゲとクロムラサキハナビラタケは、生息時期や色合いで区別することができます。
キクラゲは春から夏にかけて、特に梅雨時が最盛期です。色は茶色や濃茶色が一般的ですが、乾燥させると色が濃くなることがあります。
一方、毒を持つクロムラサキハナビラタケは秋から冬にかけての寒い時期に見られ、自生時から深い黒色をしています。
クロハナビラタケ pic.twitter.com/m9KvWSNgnt
— 方眼 (@hougan_kinoko) February 25, 2017
これらの特徴を把握し、不安な場合は触れたり持ち帰ったりしないよう注意が必要です。
キクラゲの魅力と楽しみ方

市場では乾燥したキクラゲと新鮮な状態のきくらげの両方が販売されています。雨季に採取されるきくらげは、乾燥させて年間を通じて楽しむことができます。
これまでは主に中国からの輸入品が中心でしたが、近年は国産キクラゲも増え、新鮮なものを手に入れる機会が増えています。
乾燥キクラゲは再加水することでしっかりした食感を、新鮮なキクラゲはもちもちの食感を楽しめます。
ここでは、新鮮なキクラゲの料理法と保存方法を紹介します。
キクラゲを使った料理のコツ
新鮮なキクラゲの調理にはいくつかのポイントがあります。
まず、他のキノコと同様に土台部分を取り除きます。
生でサラダに使う場合は、熱湯で30秒程度下茹ですることが大切です。
炒め物や鍋料理、スープなどに使用する際は、特に下茹でせずに土台を除去した後、直接料理に加えて熱を通すだけで十分です。
キクラゲの保存方法
新鮮なキクラゲは長期間の常温保存には適しません。鮮度を保つためには、適切な湿度を保ちつつ低温で保存することが重要です。
冷蔵保存する際は、プラスチック袋やクリングフィルムで包んで冷蔵庫の野菜保存スペースに置くと、約1週間は保存可能です。
冷凍する場合は、さっと下茹でしてから冷やし、小分けにラップで包んで保存します。
この方法なら約1ヶ月間保存でき、料理する際は冷凍のまま加熱して使用できます。
統括
低カロリーで食物繊維が豊富なキクラゲは、健康的な食事に最適です。食物繊維の含有量はゴボウの3倍にも及び、さらにビタミンDや様々なミネラルも含まれています。
日常の食生活に積極的に取り入れることで、健康維持に役立てることができるでしょう。