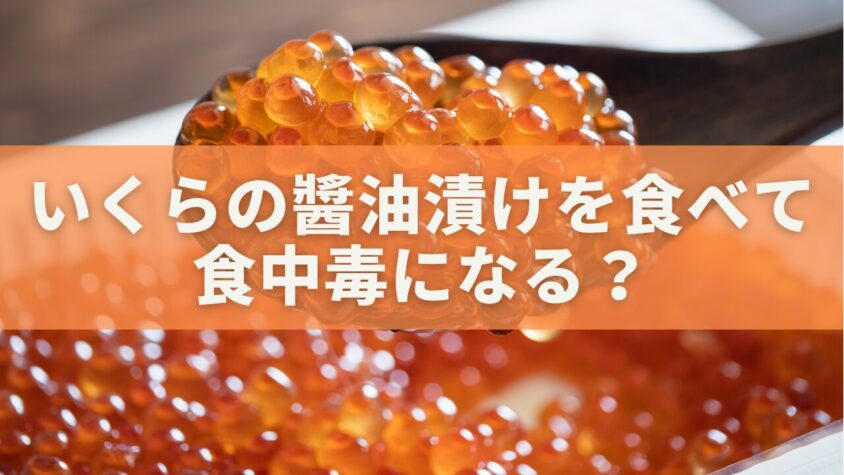秋に旬を迎えるサケの卵いわゆるいくら。その甘みとプチプチとした食感は、ご飯との相性も抜群です。寿司ネタとしても人気のいくらですが、食べる際の安全性について気になる方も多いでしょう。
ここでは、いくらの食中毒リスクについて詳しく解説します。
いくらの醬油漬け|食中毒リスクとは?

食中毒は、細菌やその毒素(あるいはウイルス)が含まれた食品によって引き起こされます。では、サケの卵であるいくらを食べた場合に食中毒になるリスクはあるのでしょうか?
過去のいくらしょうゆ漬けによる食中毒事例
1998年春から初夏にかけて、富山、東京、千葉、神奈川、大阪で約60人が食中毒を発症しました。これは腸管出血性大腸菌O157によるもので、問題のいくらしょうゆ漬けは北海道のある工場製だったことが判明しました。
このいくらしょうゆ漬けは、凍結状態で流通し寿司店などで提供される前日(または当日)に解凍されていましたが、10℃以下での保存が行われていました。生のサケ卵巣がほぼ無菌状態であったにも関わらず、いくらしょうゆ漬けには多くの大腸菌が検出され、製造過程での衛生面の問題が浮き彫りになりました。
食中毒の症状の進行
腸管出血性大腸菌O157の初期症状は、強い腹痛から始まり、数時間後に液状の下痢が現れることが多く進行すると1~2日で血便が見られることもあります。
乳幼児や高齢者では、溶血性尿毒症症候群(HUS)という重症を発症するリスクがあり、これは脳にも影響を及ぼすことがあります。HUSは通常数日~2週間以内に発生し、貧血、血小板の減少、腫れ、尿量の減少などの症状が現れます。
潜伏期間の範囲
腸管出血性大腸菌O157の潜伏期間は、平均で4日~8日間です。
食中毒症状が現れたらどうすればいい?
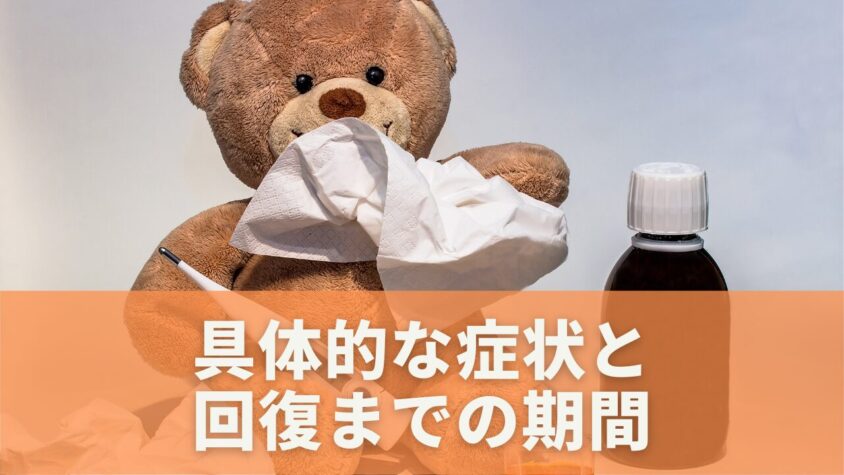
食中毒の初期症状には、嘔吐、下痢、腹痛、発熱があり、これらは体内の細菌を排出するために必要な反応で重要なのは水分補給です。嘔吐や下痢、発熱による発汗で水分が失われるため、症状が軽くなったと感じた時も水分を積極的に摂取することが必要です。
電解質と塩分を含む経口補水液の使用が推奨され、一般のスポーツドリンクよりも特に設計された経口補水液が適しています。これは、電解質濃度が高く、糖分が控えめに設定されているため、必要なミネラルを効果的に吸収できます。食中毒の症状が見られた場合は、早めに医療機関を受診することが重要です。
放置すると症状の悪化や合併症のリスクがあり、生命を脅かす可能性もあります。
【警告】
自己判断での治療はリスクを伴います。食中毒を疑った場合は、迅速に医師の診断を受けるべきです。
成人のO157感染時の回復期間
成人が腸管出血性大腸菌O157に感染しても、無症状であったり軽い下痢に留まることが多いです。
多くの場合は特別な治療を必要とせず約5日~10日で自然に回復しますが、この間O157菌が便に混じって体内に1週間~2週間ほど留まるため、他人への感染予防のために衛生管理を続ける必要があります。
食中毒時の補償について
保健所が食中毒の原因を明確に特定できない場合補償を受けるのは難しいですが、製品を販売した業者が自らの責任を認めた場合は医療費の支払いを行うことがあります。原因が正式に特定されれば、治療費や欠勤による損害賠償を受けられる可能性もあります。
食中毒が疑われる場合は、迅速に医療機関で診断を受け、原因の追求については保健所に相談することが大切です。
いくらの醬油漬けと食中毒の関連性

海産物に含まれる寄生虫は、氷点下20度で一定時間保たれることにより死滅するとされていますが、腸管出血性大腸菌O157の反応はどうでしょうか?
冷凍がO157に無効である理由
腸管出血性大腸菌O157は熱に弱く、75度以上で数分間の加熱により死滅しますが、低温には強い耐性を持っています。したがって、マイナス20度で冷凍されたとしても死滅せず、冷凍処理がO157に対して有効でないことがわかります。
総括
この記事では、いくらを食べた際の食中毒リスクについて考察してきました。
重要なポイントは以下の通りです。
- いくらを冷凍しても食中毒を防ぐことはできない場合がある
- 北海道のいくら醤油漬けによる食中毒事例
- 食中毒の兆候が現れた際の適切な水分補給と医療機関の受診の重要性
いくらは多くの人に愛される食材ですが、生産過程が衛生的でない場合は食中毒のリスクがあり、過去にはO157菌による集団食中毒も発生しています。見た目だけでは食品の安全性は判断できませんが、信頼できる生産者や販売者から購入することで、安全を確保しつつ季節の味覚を楽しむことができます。